建設業界の資金繰り地獄から抜け出す方法があるって知ってました?ファクタリングの本当の使い方
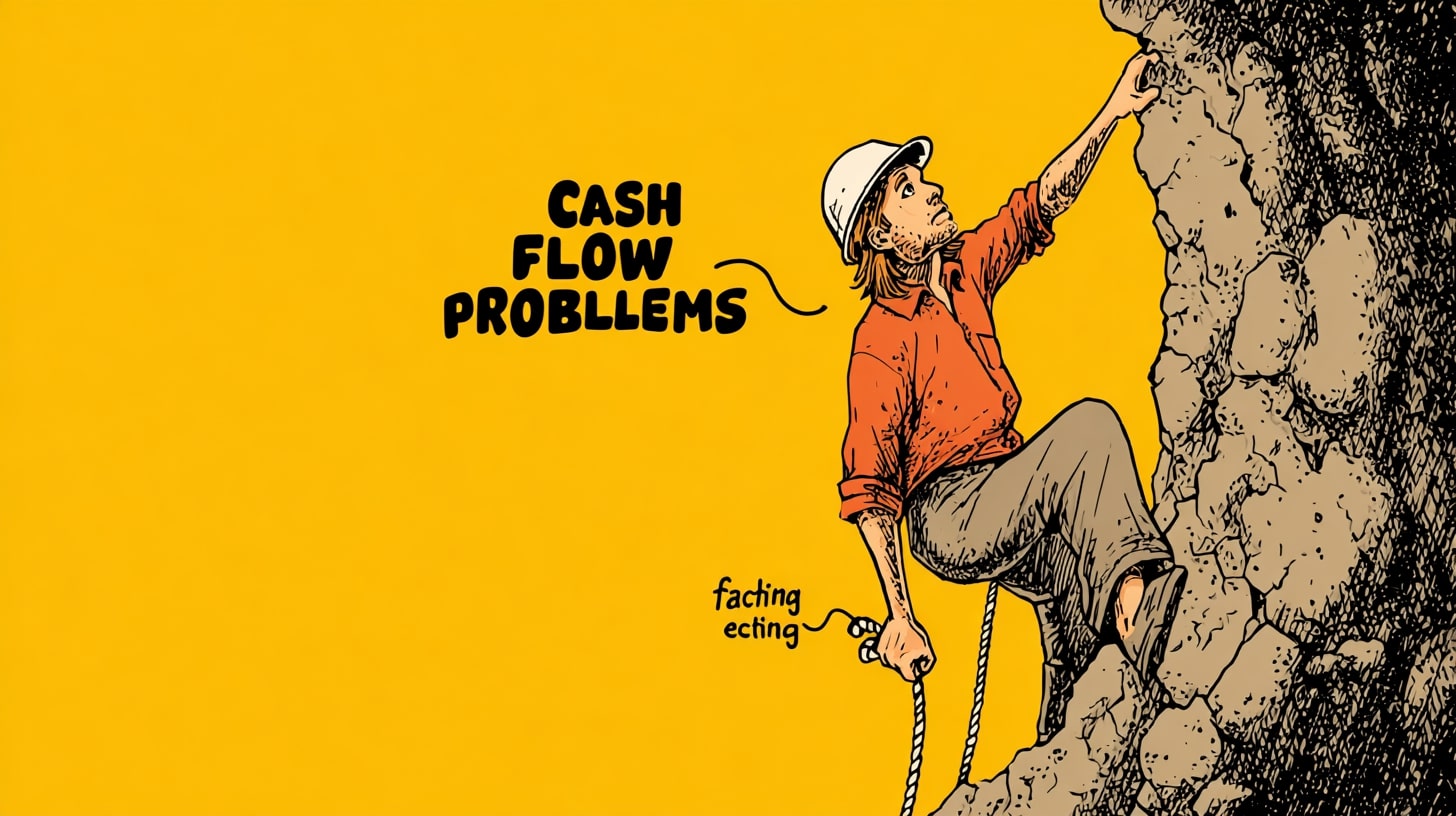
こんにちは!株式会社ドゥアイの土居です。
いやー、ほんまに建設業界の皆さん、毎日お疲れ様です。
僕も色々な業界の方とお話しさせてもらうんですけど、特に建設業界は資金繰りの話になると、どっと疲れが出るというか、根深い問題があるよなーと感じます。
「またその話か」って思うかもしれへんけど、これって避けて通れない問題じゃないですか?
職人さんへの支払いや材料費の支払い、次から次へと出ていくお金。でも、入ってくるお金は工事が終わってから、しかも手形で数ヶ月先…みたいな。
この構造的な問題、なんとかならんのか?ってずっと思ってたんですよね。
で、最近よく聞くようになった「ファクタリング」っていう言葉。
なんか怪しい金融サービスちゃうんか?とか、手数料が高いだけちゃうんか?とか、色々思うところはあるかもしれません。
でも、実はこのファクタリング、建設業界の資金繰り問題を解決する、めちゃくちゃ強力な武器になる可能性があるんです。
今回の記事では、そのファクタリングの本質的な価値と、建設業界でどう活用すべきか、僕なりの視点で率直にお話ししたいと考えます。
表面的な情報だけじゃなくて、本当に役立つ情報をお届けするつもりなので、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
建設業界の資金繰り問題の本質
まず、なんで建設業界の資金繰りはこんなに厳しいのか。その本質的な理由を3つのポイントで整理してみましょう。
1. 先行投資が当たり前の業界構造
建設業って、仕事を受注してから完成させるまで、とにかく先にお金が出ていく構造なんですよね。
人件費、材料費、重機のリース代…これらが全部、工事の完成前、つまり売上が立つ前に必要になるわけです。
大きなプロジェクトになればなるほど、この先行投資の額も期間も大きくなる。まあ、当たり前の話なんですけど、この構造が資金繰りを圧迫する一番の原因だったりします。
建設業の資金繰りサイクル
受注 → 先行投資(人件費・材料費・その他経費)→ 工事 → 完成・引渡し → 入金2. 下請け構造による支払いサイトの長期化
建設業界は、元請け、一次下請け、二次下請け…と、重層的な下請け構造が一般的です。
この構造自体が悪いわけじゃないですが、問題は支払いサイト。つまり、お金が支払われるまでの期間が、下に行けば行くほど長くなる傾向があることです。
元請けが発注者からお金を受け取るのが数ヶ月後、そこから一次下請けに支払われ、さらに二次下請けに…となると、末端の事業者さんにお金が入るのは、一体いつになるんや?という話です。
国土交通省の調査(※1)でも、下請代金の支払いに関する問題は常に指摘されています。法律で支払いサイトの上限は決められているものの、それでもなお、この問題は根深く残っているのが現状です。
3. いまだに残る「手形取引」の慣習
そして、もう一つ大きな問題が、手形取引の慣習です。
最近は減ってきているとはいえ、まだまだ建設業界では手形での支払いが残っています。
手形を受け取っても、すぐに現金化できるわけではなく、支払期日まで待たなければならない。もし、期日前に現金化しようとすれば、割引料という名のコストがかかる。
この手形という仕組みが、さらに資金繰りを悪化させる要因になっているわけです。
これらの問題が複雑に絡み合って、建設業界の「資金繰り地獄」が生まれている。これが僕の見立てです。
(※1) 国土交通省「令和5年度下請取引等実態調査」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001720849.pdf
ファクタリングって何?基本を整理してみる
じゃあ、その資金繰り問題を解決する可能性を秘めた「ファクタリング」とは、一体何なのか。
言葉は聞いたことあるけど、詳しくは知らん、という方も多いと思うので、ここで基本を整理しておきましょう。
ファクタリングの仕組みは「売掛金の売却」
ファクタリングをものすごくシンプルに言うと、「まだ入金されていない請求書(売掛金)を、専門の会社に買い取ってもらう」サービスです。
例えば、100万円の工事が終わって、請求書を発行したとします。でも、入金は2ヶ月後。この「2ヶ月後にもらえる100万円」という権利(売掛債権)を、ファクタリング会社が例えば95万円で買い取ってくれるわけです。
そうすると、あなたは本来2ヶ月待たないと手に入らなかったはずのお金を、すぐに手にすることができる。これがファクタリングの基本的な仕組みです。
ファクタリングの仕組み
2社間ファクタリングの流れ
あなた → ファクタリング会社(売掛金の売却)
ファクタリング会社 → あなた(買取代金の支払い)
取引先 → あなた(売掛金の支払い)
あなた → ファクタリング会社(回収した売掛金の送金)3社間ファクタリングの流れ
あなた → ファクタリング会社(売掛金の売却)
ファクタリング会社 → あなた(買取代金の支払い)
取引先 → ファクタリング会社(売掛金の支払い)融資とは全く違う「資産の売却」
ここで大事なのは、ファクタリングは「借金」ではない、ということです。
銀行からの融資は、お金を借りて、後で利息をつけて返す「負債」ですよね。でも、ファクタリングは、あなたが持っている「売掛金」という資産を売却する取引なんです。
だから、決算書上も負債にはなりません。これは、銀行からの評価を気にする経営者にとっては、かなり大きなメリットだと思います。
法的にも認められた安全な取引
「債権を売買するなんて、なんか危なくないの?」と思う方もいるかもしれませんが、これは民法で認められている「債権譲渡」という、れっきとした合法的な契約です(※2)。
もちろん、中には法外な手数料を取る悪質な業者もいるので注意は必要ですが、ファクタリング自体は、国が認めた安全な資金調達手段の一つというわけです。
(※2) 民法第466条(債権の譲渡性)
建設業界でファクタリングが注目される理由
では、なぜ今、建設業界でファクタリングがこれほど注目されているのか。その理由は、建設業界が抱える特有の課題と、ファクタリングの特性が、驚くほどマッチしているからです。
業界の課題とファクタリングの相性
先ほどお話しした建設業界の資金繰り問題、覚えてますか?
- 先行投資が多い
- 支払いサイトが長い
- 手形取引が多い
これらの問題に対して、ファクタリングはまさに「かゆいところに手が届く」解決策になるんです。
工事代金という、将来入ってくることが確定している売掛金を、必要なタイミングで現金化できる。これにより、先行投資の負担を軽減し、支払いサイトの長さを実質的に短縮することができるわけです。
実際の活用事例を見てみよう
口で言うのは簡単なので、実際の活用事例を3つのパターンで見てみましょう。
| ケース | 課題 | ファクタリングによる解決策 |
|---|---|---|
| 下請け業者 | 元請けからの入金が遅れ、職人への給料支払いが困難に | 売掛金を早期に現金化し、支払いを滞りなく実行。信用を維持。 |
| 一人親方 | 急な大型案件の打診。しかし、材料費などの先行投資資金がない | 受注が確定した工事の請求書をファクタリングし、資金を調達。機会損失を防ぐ。 |
| 中堅建設会社 | 資材価格の急な高騰で、運転資金が圧迫 | 完成工事未収入金をファクタリングで現金化し、急な出費に対応。 |
このように、会社の規模や状況に応じて、柔軟に活用できるのがファクタリングの強みです。
市場も急拡大している
実際、ファクタリングの市場規模は年々拡大しています。ある調査(※3)によると、日本のファクタリング市場は2024年から2033年にかけて年平均7%以上で成長すると予測されています。
これは、多くの企業がファクタリングの有効性に気づき始めている証拠と言えるでしょう。
(※3) IMARC Group「日本のファクタリング市場レポート」
https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-factoring-market
実際に使うときの注意点(ここが重要)
と、ここまでファクタリングの良いところばかり話してきましたが、もちろん注意点もあります。
というか、ここからが一番大事な話です。使い方を間違えると、逆に経営を悪化させることにもなりかねないので、しっかり聞いてください。
1. 手数料は本当に妥当か?
ファクタリングには手数料がかかります。この手数料が、業者によって全然違う。
一般的に、2社間ファクタリング(取引先に通知しない方法)は手数料が高く、3社間ファクタリング(取引先に通知する方法)は安い傾向にあります。
| 種類 | 手数料の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | 8% 〜 18% | 取引先に知られずに利用できる。審査が早い。 |
| 3社間ファクタリング | 2% 〜 9% | 手数料が安い。取引先の協力が必要。 |
この相場を大きく超えるような手数料を提示してくる業者は、正直言って怪しいと考えた方がいいです。
2. 悪質な業者を見極めるポイント
残念ながら、ファクタリング業者の中には、法律スレスレの悪質な業者も存在します。
以下のチェックリストに一つでも当てはまるようなら、その業者は避けるべきです。
- [ ] 契約書の内容を曖昧にする
- [ ] 手数料以外の不明瞭な費用を請求する
- [ ] 審査なしで即日入金を謳う
- [ ] 会社の所在地や連絡先がはっきりしない
- [ ] 償還請求権(リコース)がある契約を勧めてくる
特に注意してほしいのが「償還請求権」です。これは、もし取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった場合に、あなたがファクタリング会社にお金を返さなければならない、という契約です。
これでは、実質的に融資と変わりません。本来のファクタリングは「ノンリコース(償還請求権なし)」が基本です。ここ、絶対に間違えないでください。
3. 契約内容は隅々まで確認する
当たり前のことですが、契約書は隅から隅まで、一言一句確認してください。
もし、少しでも分からないことや納得できないことがあれば、その場で質問する。納得できる説明が得られないなら、契約しない。そのくらいの慎重さが必要です。
ファクタリングは、あくまで資金繰りを改善するための一時的な手段です。手数料というコストを払って、未来の売上を前借りしている、という感覚を忘れないでください。
安易な利用は禁物。本当に必要な時に、信頼できる業者を選んで、計画的に利用する。これが鉄則です。
ちなみに、「じゃあ具体的にどの業者がええんや?」という方のために、建設業界に特化したファクタリング会社をまとめた記事もあるので、参考にしてみてください。
参考記事:建設業者必見!信頼できるファクタリング会社8選【業界特化型厳選】
建設業界の未来とファクタリングの役割
最後に、少し未来の話をしましょう。
建設業界は今、2024年問題やDX(デジタルトランスフォーメーション)の波など、大きな変革期を迎えています。
このような変化の時代において、ファクタリングはますます重要な役割を担っていくと僕は考えています。
新しい技術を導入するにも、働き方改革を進めるにも、先立つもの、つまり資金が必要です。
しかし、従来の銀行融資だけに頼っていては、変化のスピードについていけないかもしれない。
そんな時、自社の売掛金という資産を活用して、機動的に資金を調達できるファクタリングは、企業の成長を加速させるための強力なエンジンになり得ます。
もちろん、ファクタリングが万能薬というわけではありません。でも、資金調達の選択肢の一つとして、その本質的な価値を正しく理解し、賢く活用することが、これからの建設業界を生き抜く上で、非常に重要になってくるのではないでしょうか。
まとめ
さて、今回は建設業界の資金繰り問題と、その解決策としてのファクタリングについて、僕なりの視点でお話しさせてもらいました。
もう一度、大事なポイントをまとめておきます。
- 建設業界の資金繰り問題は構造的なもの。気合だけでは解決しない。
- ファクタリングは借金ではなく、売掛金という資産の売却。
- 手数料や契約内容をしっかり吟味し、信頼できる業者を選ぶことが何より重要。
- 計画的に利用すれば、会社の成長を加速させる武器になる。
もし、今まさに資金繰りで頭を悩ませている方がいらっしゃったら、一度、信頼できる専門家に相談してみることをお勧めします。
この記事が、皆さんの会社の未来を少しでも明るくする、その一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。